
匿名
イナダさんの王道のチキンカレー(トマトオニオンベース)のカレーレシピのカレーを美味しく食べています。食べている途中で気になったのですが、このカレーはインド料理においてどのような位置づけになるのでしょうか?バターチキンなどの北インドの宮廷料理系とも違いますし、南インド系ともちょっと違う気がします。
僕が初めてお店で出すために作ったカレーがチキンカレーでした。その当時インド料理のことなんてまるで知らなかったので、僕は洋書を中心にかき集めたレシピ本からその中心値を探りました。なおかつ、ヨーグルトやココナツミルクなど材料がいろいろ入りすぎるとその中心地がよくわからなくなりそうなので、省けそうなものは全て省きました。 その結果導き出したのは、 ・鶏肉、玉ねぎ、トマトが4:2:1 というものでした。たぶんこれが本当の王道と呼べるべきものなのかもしれません。 しかしその割合で作ると少々問題がありました。バッチリおいしいけど肉が多すぎてグレイヴィが少ないのです。日本人にとってのカレーは肉よりむしろグレイヴィが大事なので、これでは売り物になりません。 なので、基本的な作り方やスパイスなどの使い方はその王道のままに、玉ねぎとトマトの割合を少し増やしたものを出すことにしました。 しかし実際はそれでも肉が多すぎる(というか汁が少ない)ようでした。 「肉少なめにしてください」 とリクエストされるお客さんも結構いて、スタッフもなんとなく無意識のうちにちょっとずつ汁多めで「カレーらしく」盛ってしまう。 結果的に鍋の中にはいつも、肉だけが余りました。 なので僕は更に玉ねぎトマトの割合を高め、結果的に ・鶏肉、玉ねぎ、トマトが5:4:3 くらいの比率に落ち着きました。 これがその後も僕にとっての中心値となりました。「王道チキンカレー」もこれがベースになっています。 その店の時、あるインド人のお客さんが言っていました。 「これはインドそのままの味だね。ただしレストランのカレーじゃなくて、インドのお金持ちの家庭の味」 自分でもいわゆるインネパ店のカレーとは全く違うことはわかっていましたから、レストランのカレーではないというのはそういうことかなと思いましたが、「お金持ちの」という部分は、インドを知らない僕にはニュアンスがよくわかりませんでした。 ただその時もし、最初に抽出した4:2:1の比率のままで、鶏肉も丸鶏の骨付きブツ切りを使っていれば、「お金持ちの」という限定は無かったかもしれません。それが王道オブ王道です。 このチキンカレーは、その後ここから生まれたエリックサウスのチキンカレーとかも含めて、インド人さんから「本場の味」的なお墨付きはよく頂きましたし、ある程度インド料理を知った自分から見てもそうだと思います。まあ実際大量のインドのレシピから最大公約数的に割り出したレシピからのスタートなので、そうならないはずがないという話でもあるんですけどね。なので、中心値から少しズレてはいても王道の範疇なのだろうと考えています。 王道、という意味には実はもうひとつの意味があります。本格的なインド料理が普及する前から東京の至る所にあった「インド風カリー」と呼ばれるもの、あるいは(ほぼ絶滅しかけていますが)僕が「名古屋地下街系カレー」と呼んでいたもの、そういうものの系譜の中にこのカレーを含めてもたぶん違和感が無い、ということです。 つまり、これは「日本人がイメージするインドカレーの王道」というニュアンスもあるわけです。 本自体は、「日本人にとってのカレーらしいインドカレー」「日本人がカレーらしくないと感じるであろうインドカレー」「今となっては日本におけるインドカレーの中心にあるであろうボイルドオニオングレイヴィのカレー」に各章が分かれています。その最初の章のトップを飾るのに、これは相応しいはず、というものです。 つまりインドを基準にしても王道で、日本を基準にしても王道で、そのベン図が重なり合う部分、ということです。




 スーパーレターでもっと届く!
スーパーレターでもっと届く!
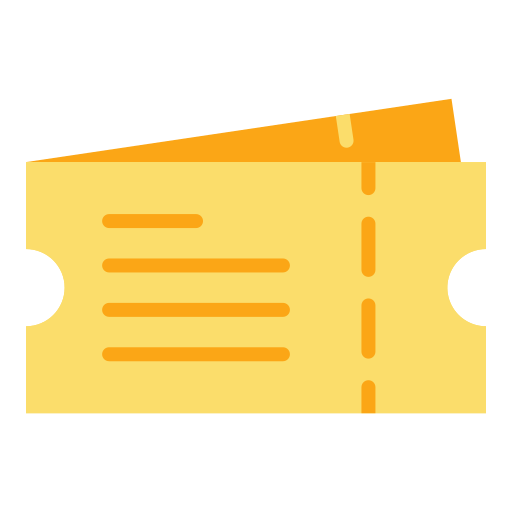 キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
 もっと見る
もっと見る
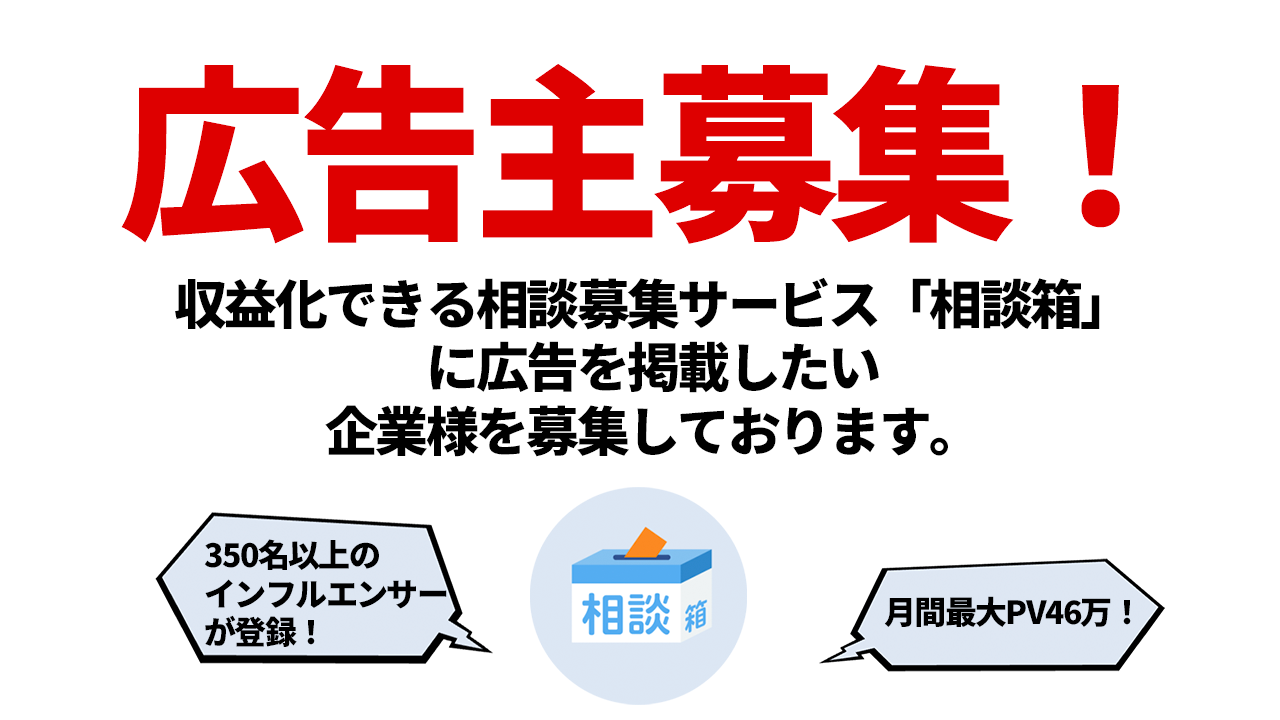
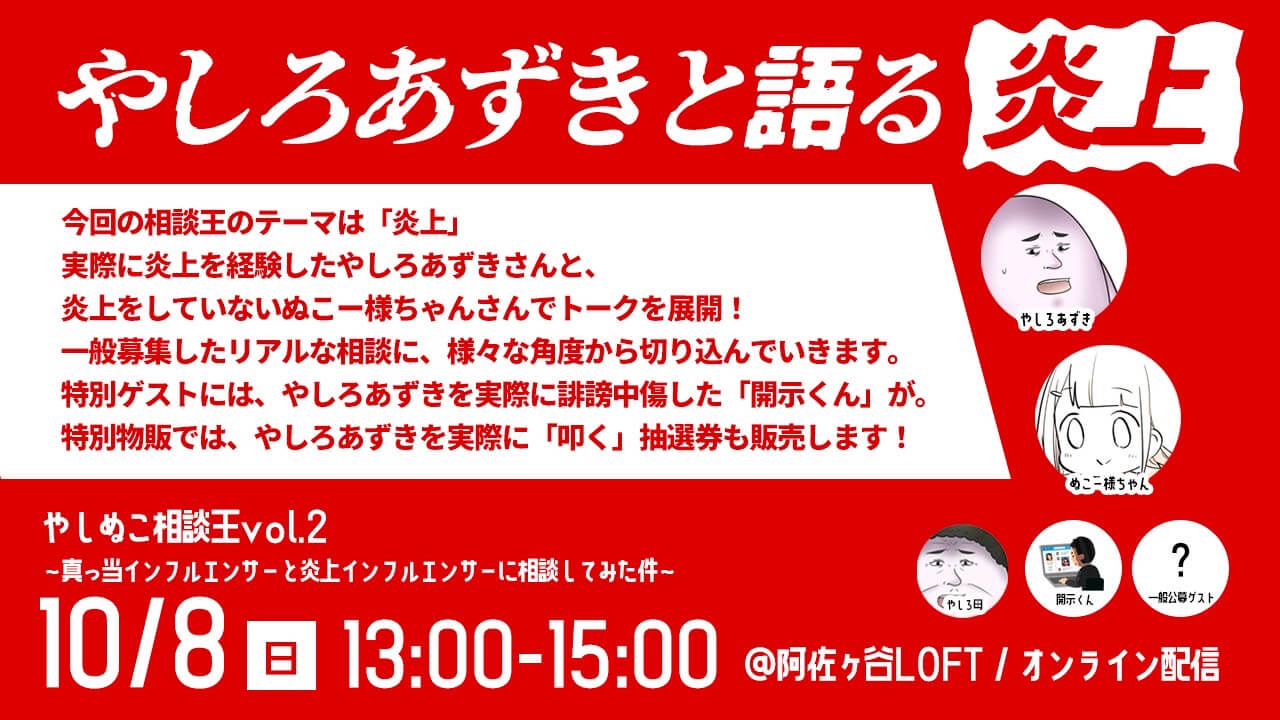

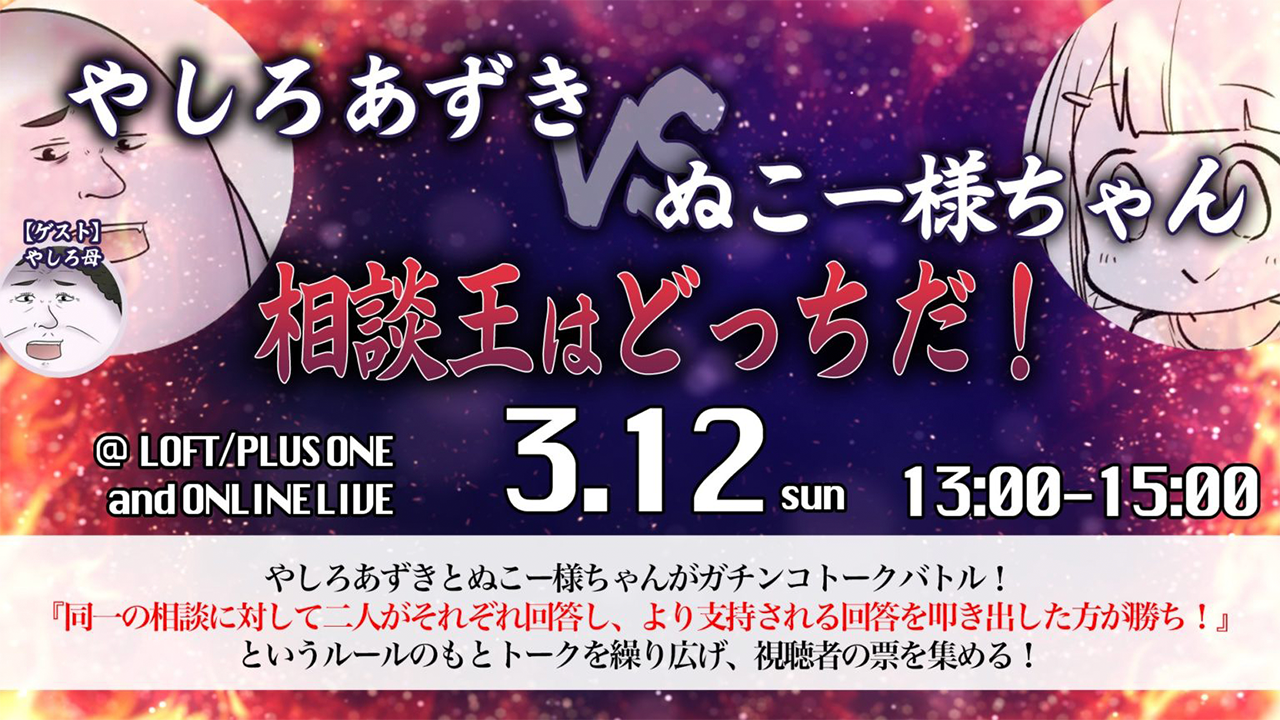

 Twitter認証でログイン
Twitter認証でログイン