
匿名
国語の教科書の盆土産という作品ご存知でしょうか。 小学校さながらあのえんびふらい の表現は食欲が掻き立てられた思い出があります。 あの文章の魅力はどこにあると思われますか?
とりあえず「しゃおっ」。 というわけでここから真面目な話をすると、『盆土産』には、ケからハレに至る、三層のレイヤーが描き出されています。 ①日常(ケ) ……「じゃっこ」をそのまま食べる ②日常の中のちょっとした贅沢(小ハレ) ……「じゃっこ」を蕎麦つゆのだしにする ③圧倒的な非日常(ハレ) ……えんびフライ(しゃおっ) もちろんメインテーマは、えんびフライの「非日常」なのですが、じゃっこの「日常」が背景として丹念に描かれるからこそ、えんびフライが一層輝くのです。 主人公が蕎麦つゆのダシにするために用意していたじゃっこの焼き干しを、父親がビールのつまみに食べ尽くしてしまったのは何故か、というのがちょっとしたミステリーになっています。 表面的には、翌日には出発しなければいけないから蕎麦を待てなかった、みたいなことが語られます。しかし父親の真意は、そんな自分のためにわざわざ手をかけてそんなものをこしらえさせるのも、という気遣いもあったのではと想像しました。もしくは、その懐かしいじゃっここそが、彼にとって海老フライ以上のご馳走だった、ということなのかもしれません。 「しゃおっ」から続く、えんびフライの「食レポ」が、なんといっても本作品のクライマックスです。 「かむと、緻密な肉の中で前歯がかすかにきしむような、いい歯ごたえ」というのは、海老フライのうまさってまさにそこ! と膝を打ちます。決して「ぷりぷり」でも「ジューシー」でもないのです。そこに続けて「この辺りでくるみ味といっているえもいわれないうまさ」というのもまた値千金ですね。旨味やコクみたいなことだけでは言い表せない、豊かな滋味を言語化するためのヒントになりそうです。 6本の海老フライを4人家族でどう分けるかとか、海老フライの尻尾を食べるかどうか問題とか、不思議と現代的なトピックも展開します。しかし結局のところ、「しゃおっ」に全部持っていかれますね。そんなところも含めて名作です。




 スーパーレターでもっと届く!
スーパーレターでもっと届く!
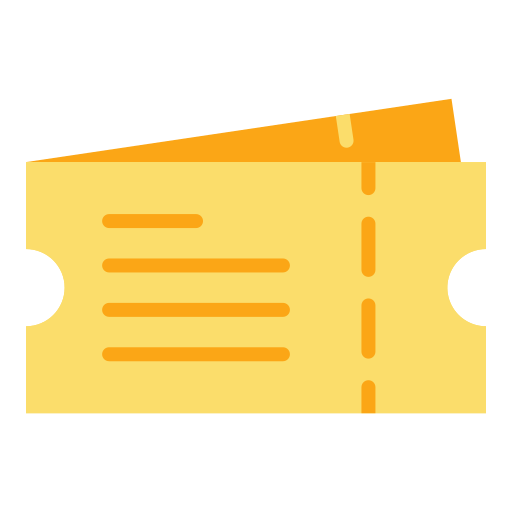 キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
 もっと見る
もっと見る
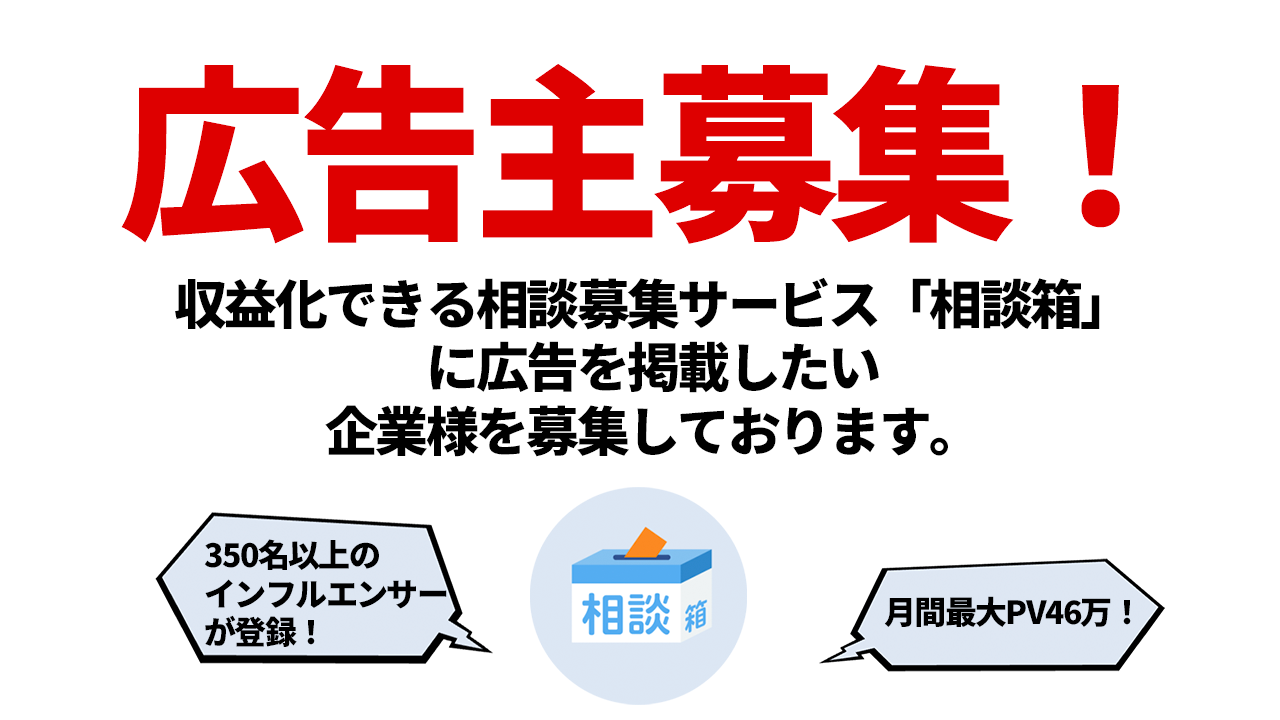
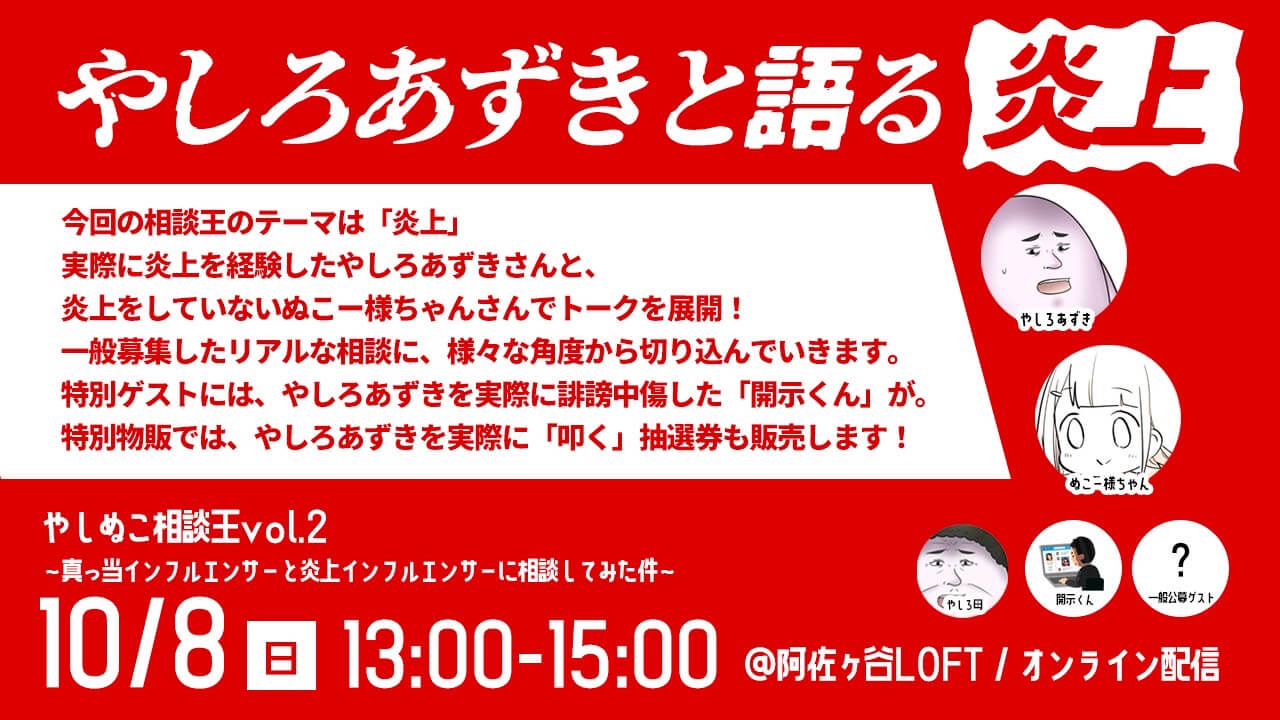

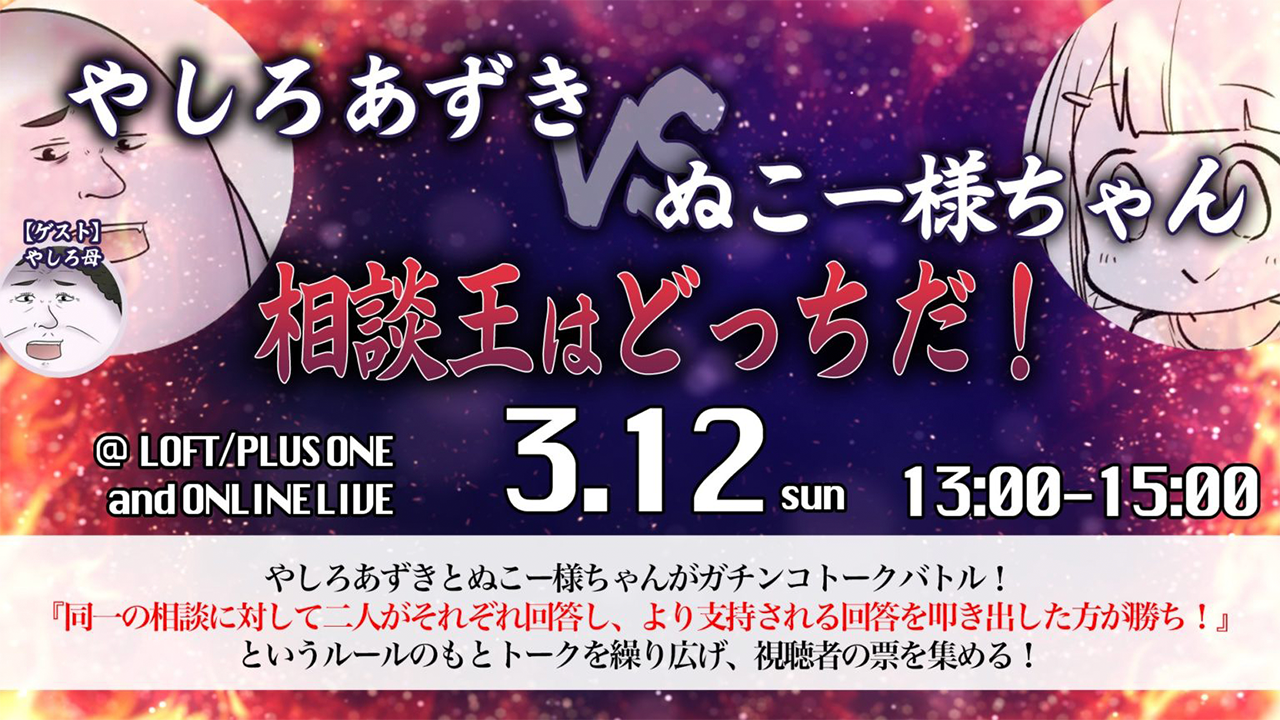

 Twitter認証でログイン
Twitter認証でログイン