
匿名
「えんみ(塩味)」という呼び方が最近広がっていますが、どこから生まれたのでしょう・・・?個人的には、芸人さんが同業者のキャラクター(人格)を指して「にん」と呼ぶときに感じるような違和感があります。
飲食業界では昔から普通に使うので、僕も普段から使いますし、一般の方が使っていても特に気になりません。ですが相談者さんとしては、シロウトがクロウトの符牒を使うのはみっともない、みたいな感覚なんだろうなと推察します。 確かに「オアイソ」とか「アガリ」をお客さん側が使うのはみっともないとされています。しかしそういう人も「ガリ」は普通に使うのではないでしょうか。他に置き換えが効きづらい、便利な言葉は、必然的に使われるようになっていくということだと思います。 「エンミ」は「シオアジ」で置き換えられるではないか、という意見もありそうですが、シオアジと言った場合、単純に調味料としての塩の味を指すと解釈するとも可能なわけです。「シオアジを効かせすぎるなよ」と言った場合「じゃあ醤油ならいいのか」みたいな誤解も生まれかねません。 歴史を遡ると、塩も唐辛子も甘みが足らないのも全部まとめて「カライ」でしたし、塩気が強すぎるのも全体に味が濃すぎるのも「クドイ」でした。これは調味料の種類も限られており、調理法のバリエーションも少なかったから、それでも特に混乱はなかったということなのかもしれません。 今は様々な味や料理があり、それに言及するための言葉にもかつてより詳細さや厳密さが求められます。言うなれば食文化の発展に言葉の進化が追いついていない状況で、例えば唐辛子もわさびも同じ「カライ」なのはたいへん不便だったりもします。 そんな中で使える言葉はなるべく使おうとなると、「エンミ」はとても便利な言葉のひとつです。山椒の辛さに「シビレ」が採択されたのと同様、これは日本語の進化なのではないでしょうか。




 スーパーレターでもっと届く!
スーパーレターでもっと届く!
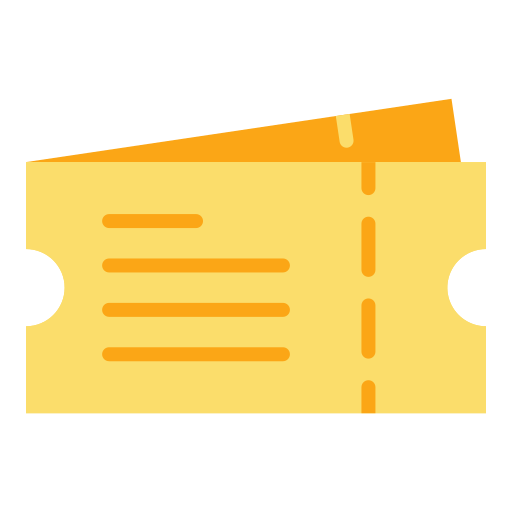 キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
 もっと見る
もっと見る
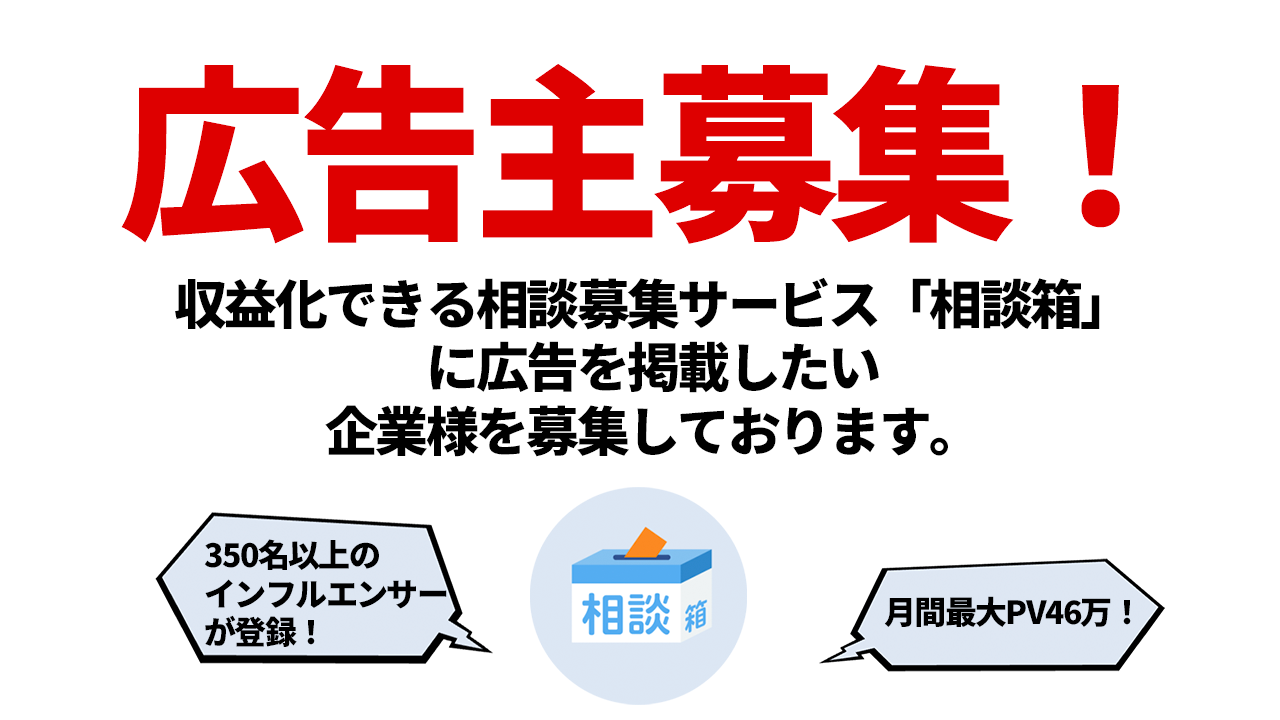
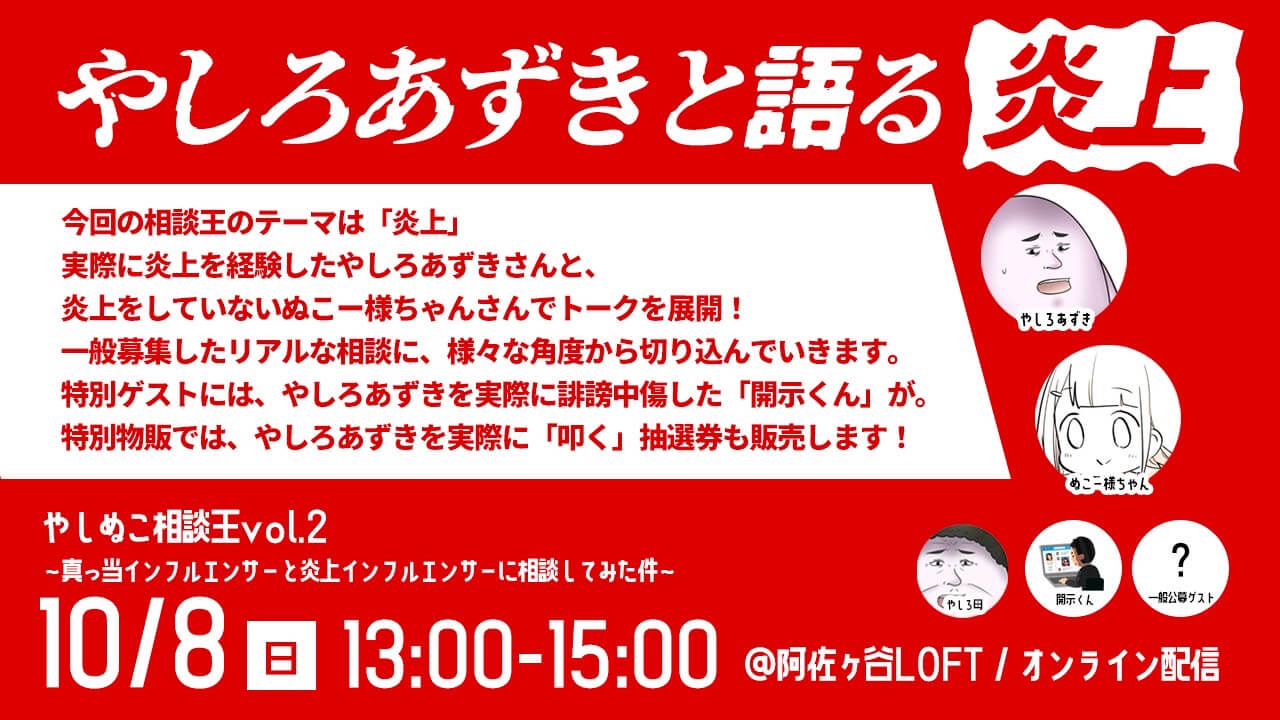

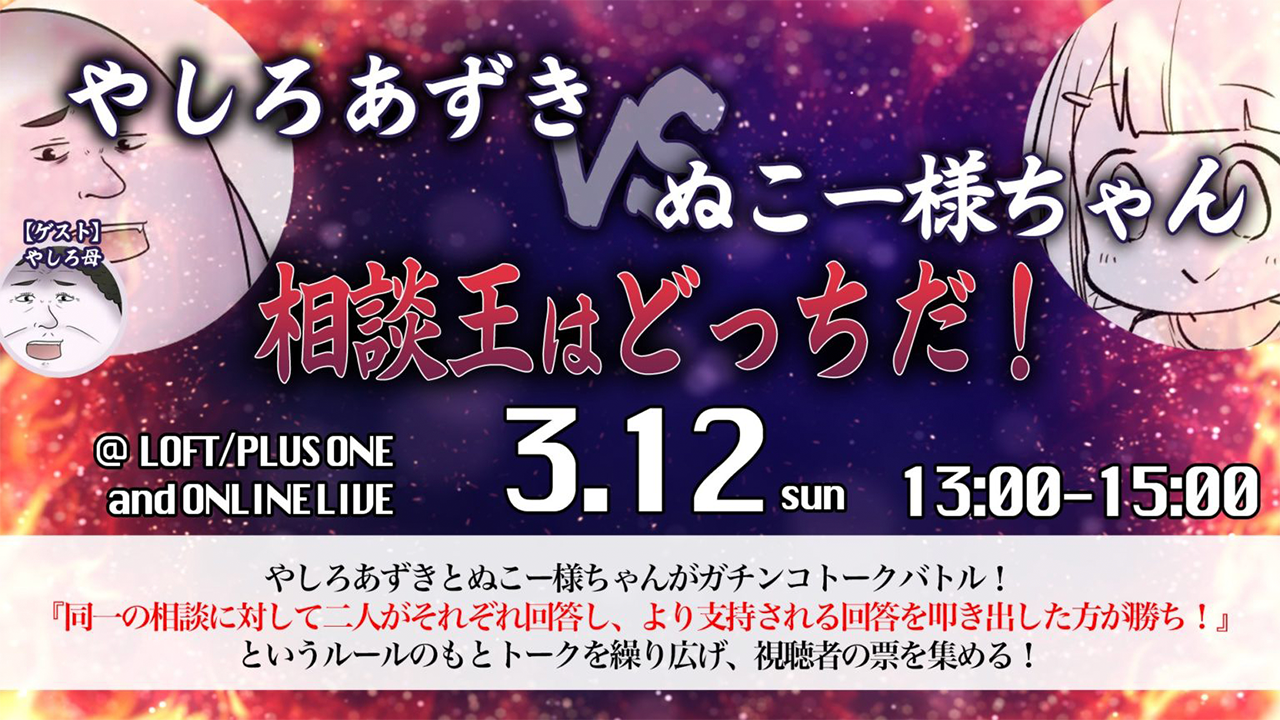

 Twitter認証でログイン
Twitter認証でログイン