
でゅえろう
鍋、と称する料理のスタイルが変化してしてきた気がしています。以前、家庭で食されてきた鍋は具材を山盛り鍋の横に準備して、鍋の中身が少なくなっては足してを繰り返すスタイルだったように思いますが、現在はひとつの鍋に具材とスープを詰めて煮あげて無くなったら終わり。「鍋料理」の定義ってどう思いますか?
囲炉裏に吊るされた鍋の中では野菜のごった煮汁がぐつぐつと煮え、それを家族が取り囲むーーこれが原初の鍋です。その後江戸などの都会では、単身者のための外食のひとつとして小鍋が生まれます。これはぐっと洗練されたものになりましたが、基本は囲炉裏の鍋の小型化です。 外食における鍋はさらに発展し、複数人で囲む料理としての鍋が成立しました。ここで初めて、具材を大皿に豪華に盛り付け、順を追ってそれを投入していくスタイルが生まれました。ガスの普及もそれを後押ししたことでしょう。 鍋というのはあれで案外技術やコツが必要なもので、そういう店では仲居さんがその技術をマスターし、お客さんの鍋の世話をしました。 特に高度な技術を要するのが「すき焼き」で、今でもあるすき焼きとしゃぶしゃぶの有名店では、すき焼きを取り仕切れるのは仲居さん達のごく一部だそうです。 そんなもてなしの鍋は、戦後、家庭料理としても一般化しました。そこで仲居さんに変わって鍋を取り仕切ったのは「主婦」です。良妻賢母の時代です。 すき焼きだけはお父さんが仕切るというのも昭和の風景でした。イギリスでローストビーフだけは亭主が取り仕切るのと似ていますね。日本の場合、外食で仲居さんの高度な技術に接していたのはほぼ男性のみだった、というのもあるでしょう。 小うるさく口出しをするくせに全てを取り仕切るわけでもない「鍋奉行」が揶揄され始めたのもこの時代です。 時代は移り、専業主婦は激減しました。家事において女性ばかりが重い負担を強いられる傾向は薄くなっていきます。そうなると、食事の間も仲居さんのように家族の世話を焼き続けなければいけないスタイルは、過去のものとなっていきます。 それに世帯人数も減り、具材の総量も、ひと鍋に一度に収まる程度で十分となりました。 こうして、鍋が原初の形を取り戻すことになったのが現代、ということが言えるのではないでしょうか。




 スーパーレターでもっと届く!
スーパーレターでもっと届く!
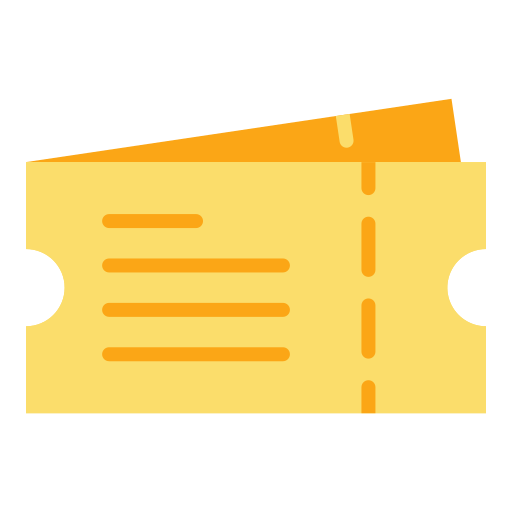 キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
キャンペーンコードをお持ちの方はこちら
 もっと見る
もっと見る
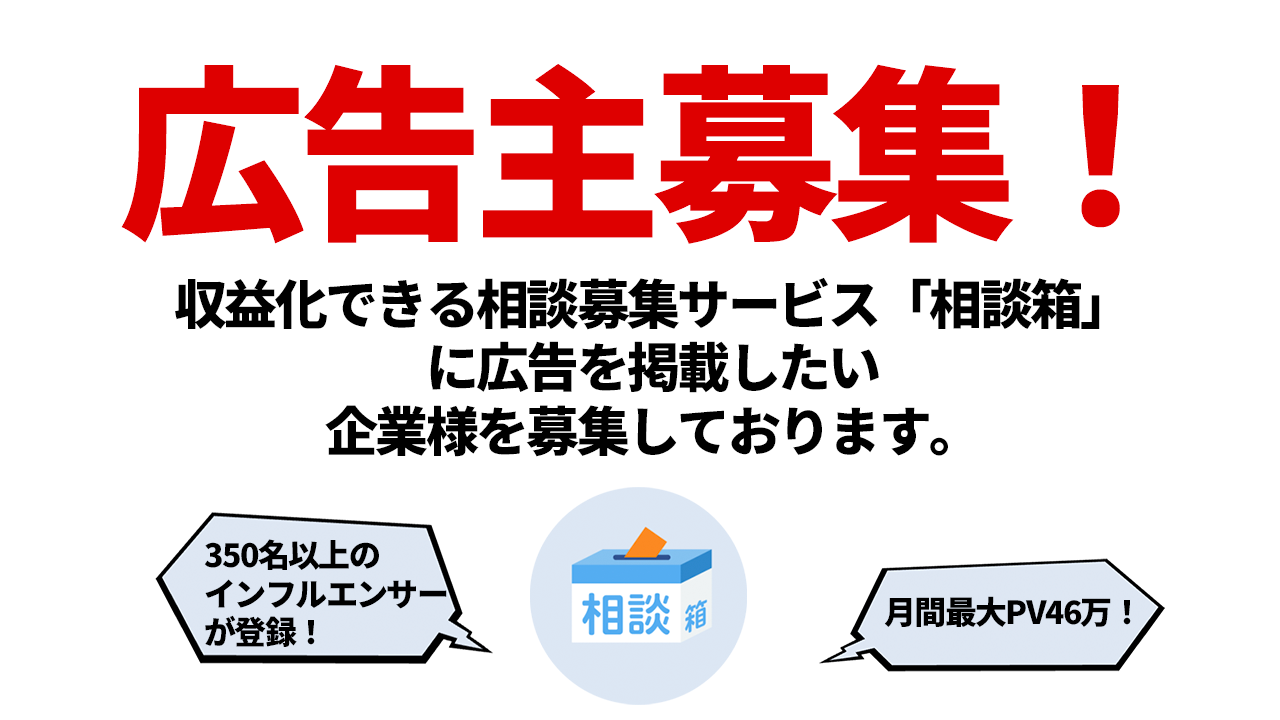
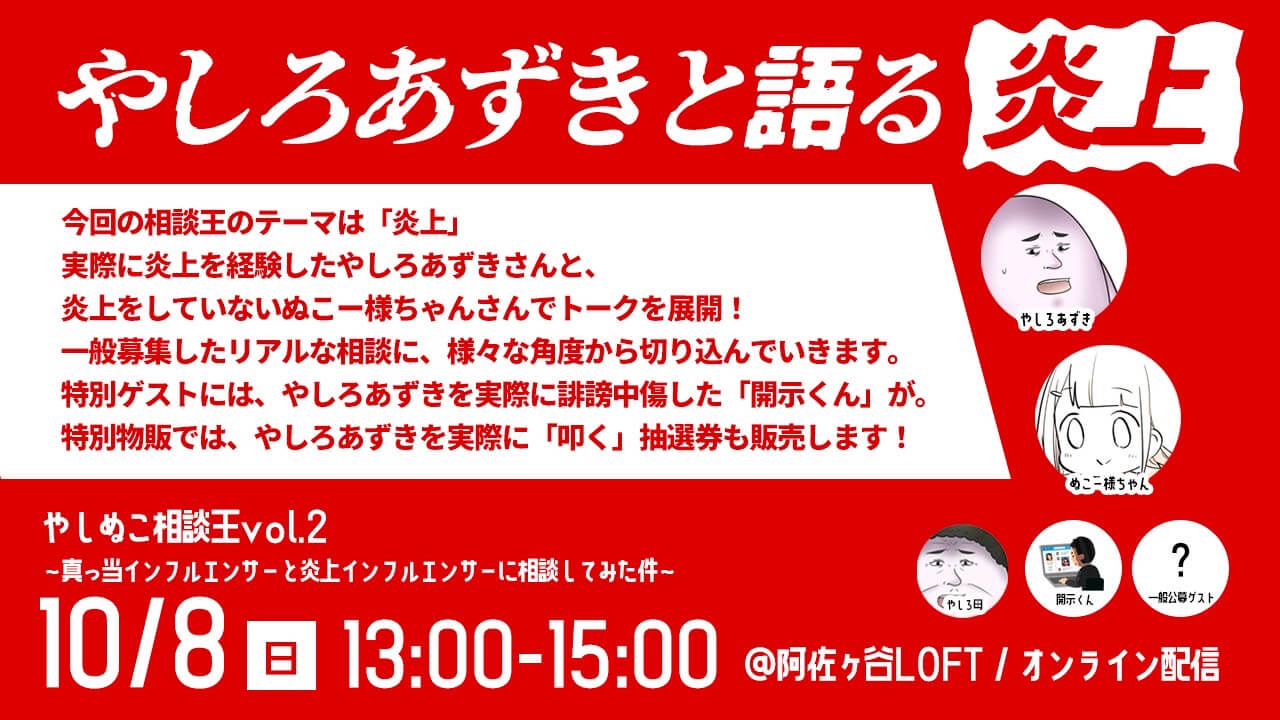

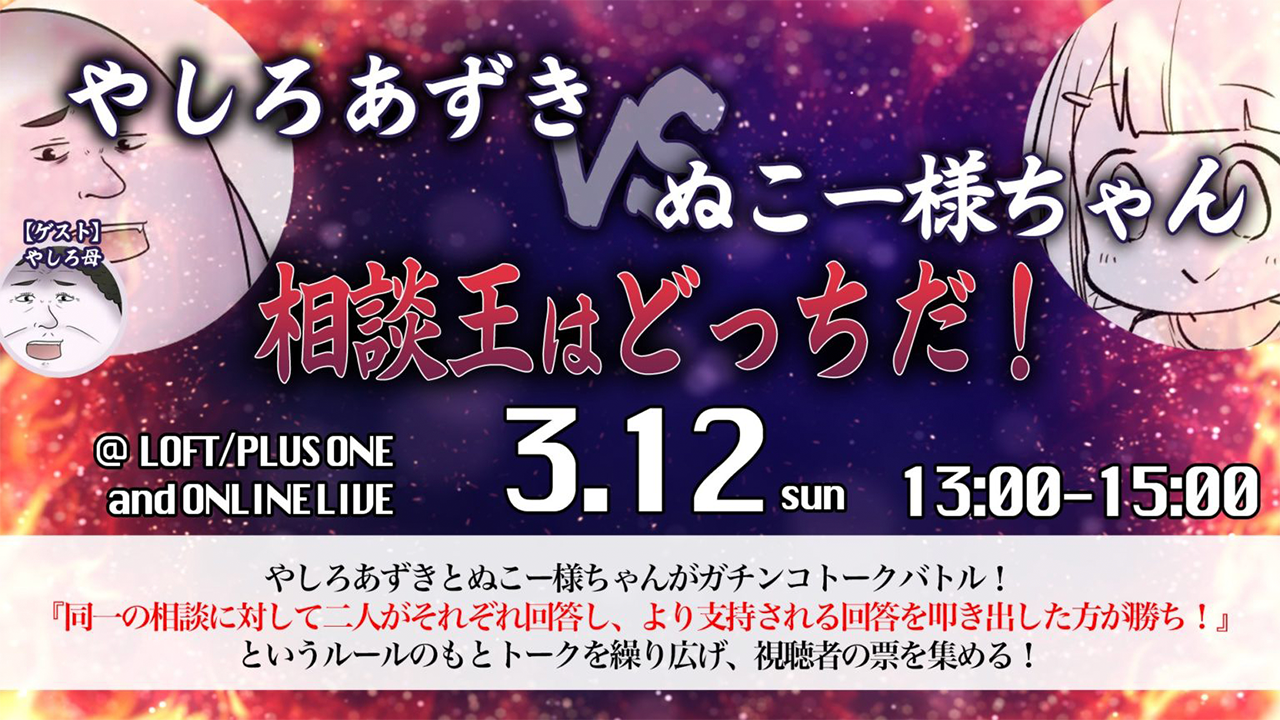

 Twitter認証でログイン
Twitter認証でログイン